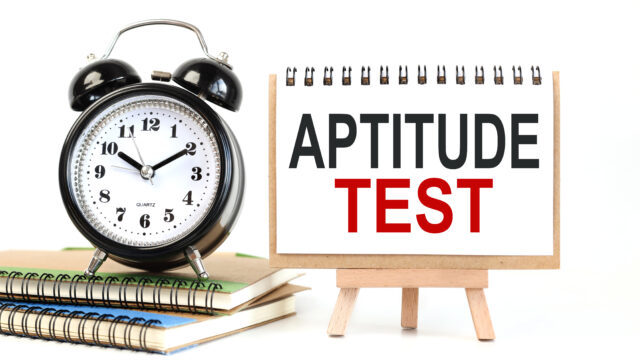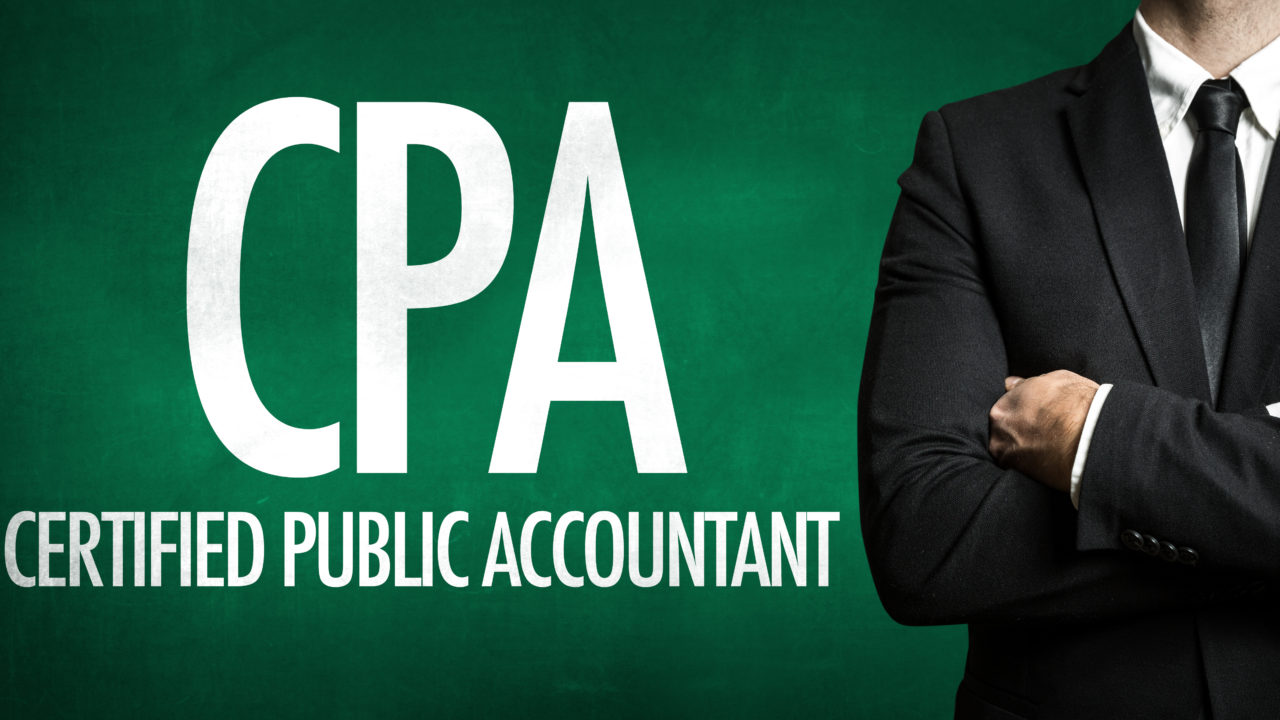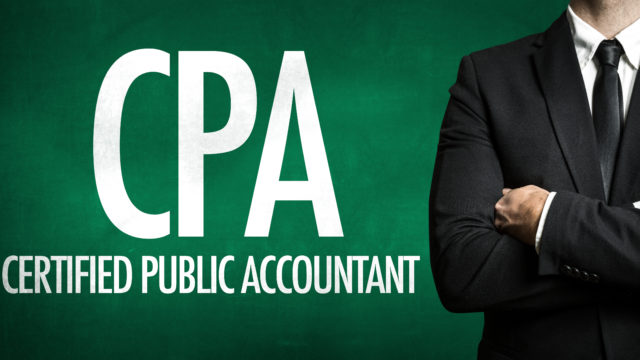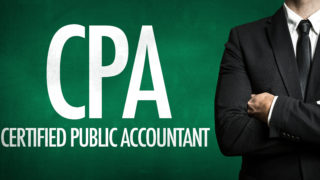USCPA(米国公認会計士)を目指す人が増えていますね。
きっと皆さんキャリアアップや自己研磨に励んでおられるのでしょう。
USCPAは最近は日本でも受験できるようになりましたから、日本人にも結構身近な資格になった気がします。
各予備校が受験生集めに必死で、USCPAは簡単だとか勉強すれば受かるなどUSCPAの難易度が低いような言い回しを聞くことがあります。
そんな予備校のうたい文句に乗って軽い気持ちでUSCPAの学習を始めた人がどれほど挫折していることか。私もBECは全く受かる気がしませんでした。
発表されている合格率や予備校の宣伝文句に乗らず自分自身で取得を目指すかどうか決めていきましょう。
【結論】挫折率が高いのは予備校の広告に振り回されているから。
予備校の広告を並べてみます。
グアム大学
アビタス
TAC
大原

これなら何となくUSCPA=簡単=合格しやすい
というイメージを持つのは当然です。
【理由】日本語でのUSCPAに関する情報源が予備校くらいしかない。
AICPA発表のデータは下記になっています。
2020年のUSCPAの合格率は以下の通りです。
| 科目 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| AUD(監査) | 47.97% | 65.29% | 56.89% | 47.50% |
| BEC(ビジネス) | 61.76% | 76.92% | 69.89% | 60.77% |
| FAR(財務会計) | 46.37% | 62.86% | 55.67% | 43.53% |
| REG(税法) | 55.42% | 75.97% | 66.12% | 58.00% |
これだけ見れば受かりやすいと勘違いするのもうなづけます。
合格率は受かりやすさに関係ない【USCPAが求めている合格基準を理解する】
こんな情報を見せられたら自分も簡単に合格できそうだと思うことは当然でしょう。
それなのに全然合格できない・・・合格するイメージも持てない。
自分はダメなんだ。
こんなに合格率が高い試験にも合格できないだ。
なんて悲痛な声が聞こえてきそうです。
そんなふうになかなか合格できずに自信を無くして挫折してしまう人が後を絶ちません。
最初に「USCPAは簡単だ」なんていう刷り込みを受けているので余計ダメージがデカい。
でもそんな悲観的になる必要はありません。
確かに、USCPAは各予備校が宣伝しているほど簡単に取得できるものではありません。
「合格率が高い=受かりやすい=簡単」ではないです。
しかし、簡単に取得できないからと言って、ひっくり返っても逆立ちしても取得できないかと言えばそんなこともありません。
合格の秘訣は合格に必要な知識を固めることです。
これは合格基準が分かっていないとできません。
なんといっても試験範囲が膨大です。
全部を完璧にして試験に臨むことは普通の人はできないでしょう。
そんなことをする必要もありません。
完璧にしたければ合格後に仕事をしながら実務の中で完璧にしていけばいい。
多くの人はこれまた予備校の擦り込みによって、「MC(マルチプルチョイス)を回せば合格できる」と教えられてきたことと思います。
もちろんMCは大事です。
相当なスピードでこなしていかないと全部解けないからです。
しかし!
この「MCを回せば受かる」という信仰に陥ると、なかなか合格できなくなります。
なぜならMCを回すことに集中してしまうからです。
何度も何度も同じMCを回しますが、答えを覚えているので回答はできますし、なんとなく勉強した気にはなります。
こういう方が本番の試験でビックリすることになるのです。
そうです、実は同じ問題が出ないんです。
たまに過去問の焼き直しが出ますが、それは解けて当然のスーパーサービス問題です。
そんな問題が解けなかったら確実に落ちます。
USCPAの合格基準が分かっている人はこういう問題は確実に得点します。
USCPAは難しい問題は解けなくても合格できます。
しかし、難しくない問題、ちょっと考えれば解けそうな問題、あ、これ見たことあるな的な問題は得点出来なければ落ちるのです。
ここの見極めができない限りたぶん受かりません。
そう、MCにも重要度があるのです。
レベル1:絶対に落としてはいけない問題(落とすと速攻で不合格になる問題)
レベル2:解けないと合格が厳しくなるかもしれない問題(少しの応用問題)
レベル3:合格する人を高得点で合格させるための難しい問題(発展問題。考えれば分かりそうな問題)
MCにはこれらレベル1~レベル3の3つのレベルがあると思ってください。
このうち、レベル1を落としたらもう受かりません。
だからこのレベル1の問題は死守です。
レベル2もそこそこ取れないと受かりません。
だからレベル2が踏ん張りどころ、合否を分ける境界線と思って頑張って解いてください。
レベル3は趣味の問題です。
解けても解けなくても合否には影響しません。
時間が余ったり、余裕がある人は解いてもいいでしょう。
ちなみに私は「あ、これはレベル3だ!」と思った問題は問題もろくに読まずに「C」を選択して次の問題に行きました。
どうせ解けないし、解いたところで合否に影響ないし、どうせ解くにしても時間がかかるのでだったら最初から解かなくても同じだということでちゃんと見ることもありませんでした。
その代わりレベル1は2回見直しして確実に得点するようにしましたし、レベル2の問題もなんとか勉強した知識を総動員してできるだけ頑張って解きました。
それで高得点ではないけれどなんとか合格できたのです。
ちなみに最初は私もMC信者だったので、MCを回すことが目的になっていた時期がありました。
しかし、2~3回受験した時に気が付いたことは、MCで勉強した問題と全然違う問題しか本番では出題されないということです。
それで悟りました。
MCを回すことは合格に直結しないと。
そこで学習方法を変えました。
予備校の教科書に載っている問題だけを何時間もかけてじっくり解くようにしたんです。
予備校の教科書に載っている問題は基本問題です。
私のレベル分けで言えば、レベル1~2くらいでしょう。その代表とも言える問題が載っていることが多いです。
例題ですから量もそれほど多くないでしょう。
まさにこれが吉と出ました。
問題数は少ないものの、どういう意図で出題された問題なのか、なにを問いたいのかなど色々出題者の意図を考えながら解くことで、USCPAが試したいと思っている内容というかUSCPAの門をたたく人にはこれは知っておいてもらわないといけない内容というものが見えてきたのです。
出題者の意図さえつかんでしまえば簡単でした。
あとはその意図に合わせて数字を入れ替えたり、出題視点をずらしたりしているだけだと分かりました。
出題意図は1つですが、出題角度といいますか出題視点は無数に作れるのです。
その無数に作られたのがMCなので、MCから出題者の出題意図、出題の目的が分かる人であればMCを回している中で出題者の意図にたどり着くことができるかもしれませんが、MCを回すことに集中してしまう人は、この出題者の意図をつかむことができず、ただただ問題を解くことになり、結果的に違う角度や違う視点から出題されてしまうと、同じ出題意図なのに全く違う問題に見えて本番で解けなくなってしまうのです。
この出題者の意図を見抜けるようにならないとUSCPAの合格は厳しいものになります。
USCPAに受かる気がしない場合の具体的対処法
これ、気持ちは痛いほどわかります。
個人によって得意・不得意があります。
FARが得意な人もいれば、AUDが得意な人もいるでしょう。
そういう意味では私はほとんど得意な科目はありませんでした。唯一AUDだけは一回で合格できましたが、それ以外の3科目は全て3~4回は受験しました。
これだけAICPAに貢献した日本人受験者も珍しいのではないかと思います(涙)。
そんな私から「USCPAに受かる気がしない」「USCPAの勉強に挫折しそうだ」という方にアドバイスさせてもらうとすれば、以下です。私自身が何度も不合格した経験から気が付いた勉強法です。これを実践してからなんとか合格できました。
基礎に帰る
AICPAのリリース問題を徹底的に研究する
解くべき問題を見極める
基礎に帰る
これが一番大事です。
USCPAは米国公認会計士になるための登竜門です。
そのために、あの手この手であなたがその登竜門をくぐるのに適切な人物かどうかをチェックしてきます。
なぜそのように「あの手この手」を使ってくるのか。
それは登竜門をくぐるのに適切じゃない人には受かってほしくないからです。
USCPAは会計の専門家の資格であり、証券市場の番人として機能する大事な使命を負っています。だからその使命にふさわしくない人にはUSCPAになってほしくないわけです。
つまり、「マグレ合格者」をできるだけ排除したいということです。
そのために試験には様々な工夫=からくり=仕掛けが仕込まれています。
まだ合格に及ばない人はこのからくりに騙されてしまうのです。逆に合格レベルに達している人はこの仕掛けに騙されずに、きちんとすり抜けられる能力を備えています。
この能力を磨くために必要なことは一つ。
それは基礎を徹底的に固めること。これに尽きます。
どんな試験でもそうですが、出題者側が「これはできてくれないと絶対に合格させたくない」という問題が存在します。
それが基礎問題です。
ところが、ここで勘違いしてほしくないのは、「基礎問題=簡単な問題」というそんな単純なことではないということです。
出題者側としては、きちんと基礎ができている人に合格してほしいと思っています。
しかし、基礎的な問題を基礎的に聞いても、結構解ける人が多いと思います。なぜなら基礎的な論点は基本的にはみんな少しは勉強しているからです。
だからといって、基礎的じゃない問題ばかりを出題しても、結局解ける人が少なくなり、結果的にマグレ合格者=基礎が分かっていないのにタマタマ合格してしまう人を輩出するリスクが残ってしまい、出題者側の意図とズレてしまう可能性があります。
そこで、出題者側は、出題の論点としては基礎的で、誰もが知っているポイントだけども、出題の仕方を工夫することで、本当に分かっている人じゃないと正解を導きにくいように設計された問題を出題するのです。
これによって、基礎がちゃんと分かっている人は、この仕掛けには騙されずに「あー、これはあの論点を聞いてきているな」ということですぐに解答方法が分かるのですが、基礎をしっかり勉強していない人にしてみれば、なんだか難しい問題に見えてしまって、論点がはっきり見えずに空回りしてしまうという事態を引き起こします。
これが「勉強はちゃんとしているのに受かる気がしない」と思ってしまう人が陥ってしまう罠でしょう。これの解決法は、基礎に立ち返って論点を見抜く練習をすることです。
これは闇雲に問題の数をこなすよりも、テーマごとの論点をきちんと深堀して、良質な問題だけを繰り返し解いて、そのテーマの論点と設問の角度を確認する勉強に重点を置くといいでしょう。
基礎的な論点をその出題範囲を超えずに難しく見せるのは、「出題の角度を変える」ことにあるからです。
同じ論点でも出題角度を変えるだけで無数の問題を作ることが可能となります。
しかし、分かっている人からすれば同じ論点を扱っていることには間違いないので、どんな角度から出題されてもスラスラ解けてしまうのです。
分かっていない人は角度が変わると回答できなくなってしまいます。これは本当の意味でその論点を理解しているとは言えませんね。そういう人はまだまだ合格が遠いということになります。
AICPAのリリース問題を徹底的に研究する
次に勧めたいのが、AICPAのリリース問題を研究することです。
AICPAのリリース問題は今後試験に出題するかもしれませんよ~という新種の問題を予めサンプルとしてAICPAがわざわざ公開してくれているものです。
ご存じの通り、世の中は刻一刻と変化しています。
証券市場を守らなければならないUSCPAとしても、世の中のトレンドや流れについていくことは必須の課題です。CPE制度があることも当然となりましょう。
USCPAの試験は過去の膨大なデータベースの中からランダムに出題されるわけですが、毎回新しい問題も一定数は入れていかなければならないのですが、突然出題するのもかわいそうなので、事前に予告してくれるわけです。
「昨今の世界情勢を踏まえて、今後はこういう問題も出していきます」というAICPAからの宣言です。
わざわざ出題者が「出しますよ」と言っているのですから、これを勉強しておかない手はありません。
それほど数が多いわけでもありませんから、試験の直前1週間くらいから始めて試験本番までの1週間で研究してみるのがいいと思います。
ラッキーであれば、そのまま出題されるかもしれませんので。
解くべき問題を見極める
USCPAに合格するための最終テクニックとしては一番大事なのがこれです。
つまり、全部の設問を同じ目線で見ない、ということです。
合否を分けるのはこの時間の使い方のメリハリと思います。
よく1問90秒で解けとか60秒しかかけられないとか言われたものですが、正直試験を何回も受けた自分から言わせればそんなのは外野が騒いでいる戯言と言わざるを得ません。
正直言って、本番を受験している受験生にそんなカウントする余裕はありません。
この記事を見てくれている人は、きっとUSCPAを諦めようかと思っている人が大半だと思うので、私の意見に賛同してくれるでしょう。
だからこそ最初から解く問題、解かない問題をまずは決めてしまうことです。
当然ながら「解く問題」は基礎的な論点の問題です。ここを落としてしまうとほぼ合格は難しいと思ってください。これは75点前後を決めるとても大事なクリティカルな問題なので、ここに全神経を集中させてください。
逆に基礎的な論点ではない問題は、ボーナス問題です。
80点の人を85点で合格させるか、90点で合格させるかを決める問題なので、合否には既に関係ありません。だからこういう類の問題は時間がないなら適当に好きなアルファベットに印をつけて進んでしまって構いません。こんな問題に時間を使うくらいなら、ちゃんと基礎的な論点の問題に時間を使ってください。
いいですか。
75点を取る問題を解かずに、90点を取る問題を解いても受かりませんよ。
その理由は先程説明した通りです。
マグレ合格者は輩出したくないし、基礎ができていない受験生をUSCPAにさせたくないからです。
逆に75点を取れる能力が備わっている=基礎ができているという受験生なら合格させてもいいかなと思います。
なぜなら基礎ができているので、その基礎の上に実務を通して積み上げていくことで開花することは十分に可能だと思っているからです。その逆はありません。
まとめ:予備校の広告にだまされないで!USCPAはそれなりの学習と戦略が必要です。
今日のまとめです。これで合格までの距離が最短になることを祈っています。
問題のレベル分けができるようになるまで練習する。
レベル1とレベル2を確実に解けるように練習する。
レベル3は余裕がない限り時間を掛けない。
出題者の意図をつかむ練習をする。
MCを回すことだけにこだわらない。
もっと勉強しないと不安になるかもしれませんが、落としてはいけない問題を確実に正解すれば、高得点で合格できないかもしれませんが不合格にはならないでしょう。
それほど基本的な問題を落とさないことが合格への近道となるのです。
【USCPAについての質問!】米国公認会計士(USCPA)に関するよくあるQ&Aまとめ